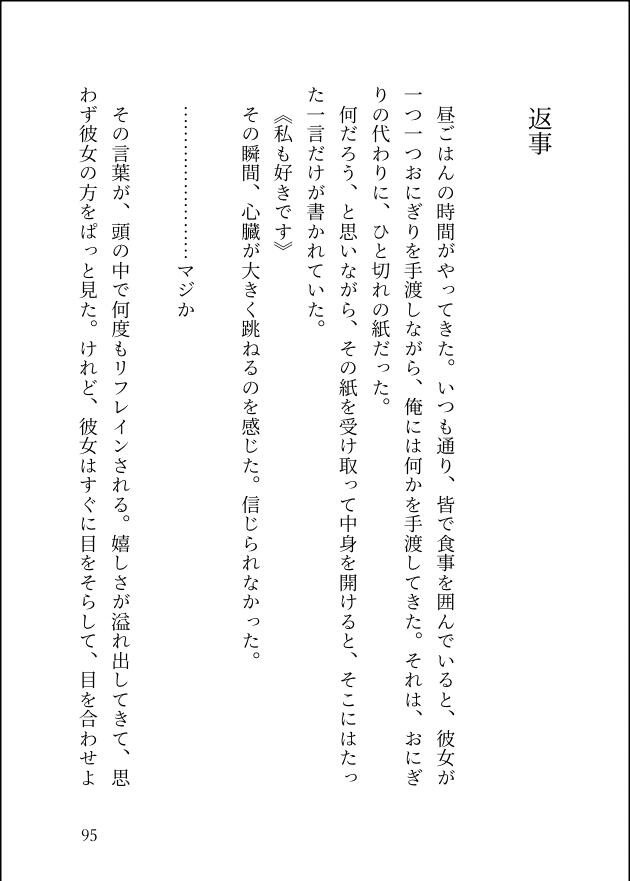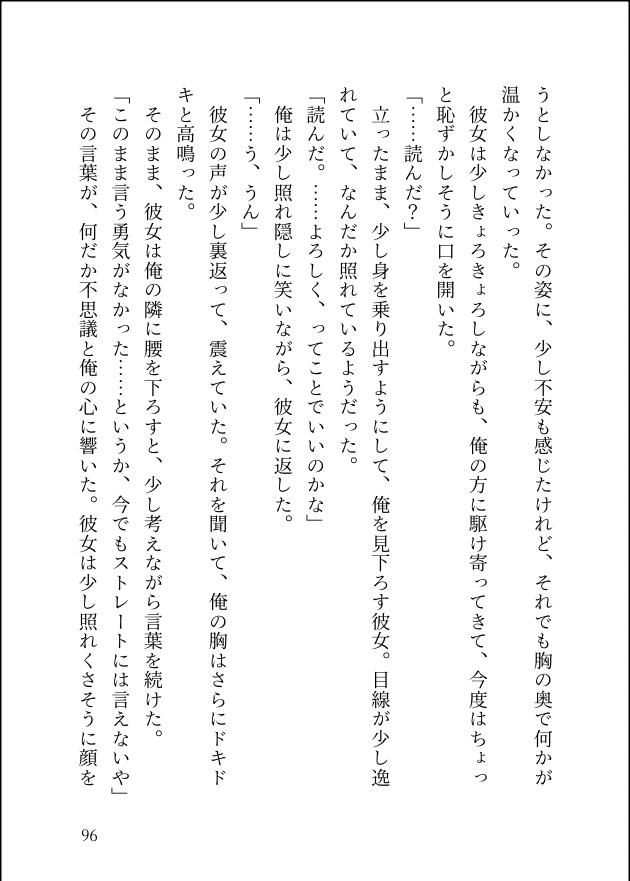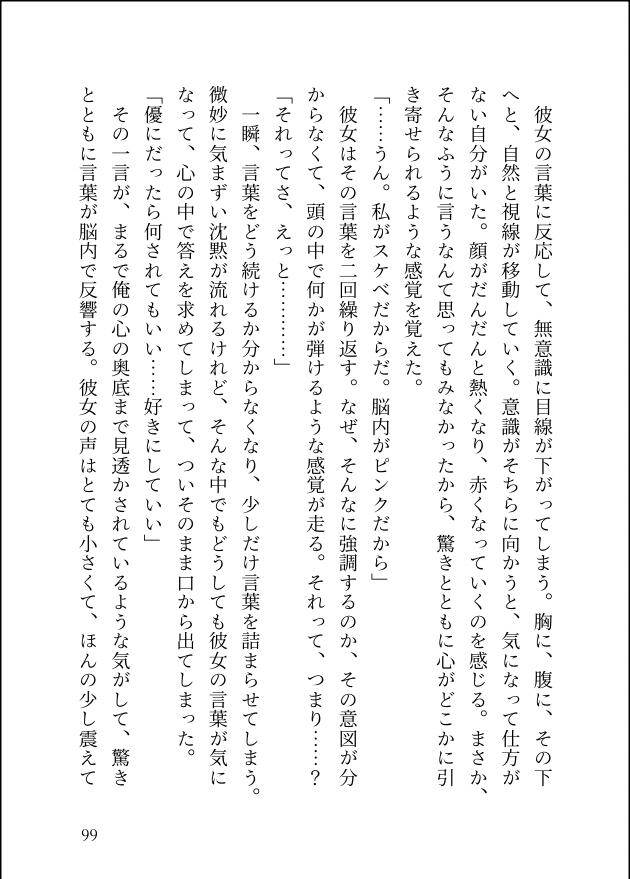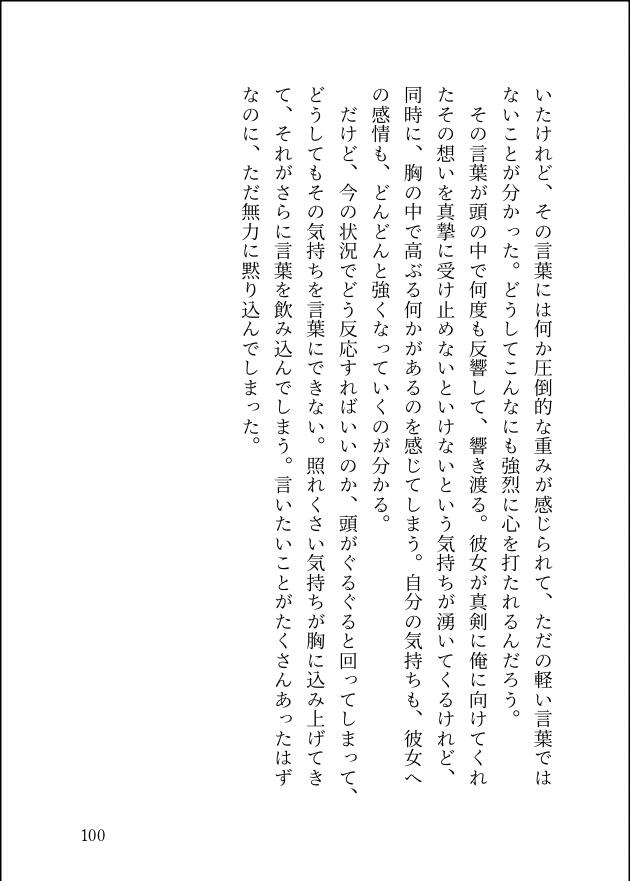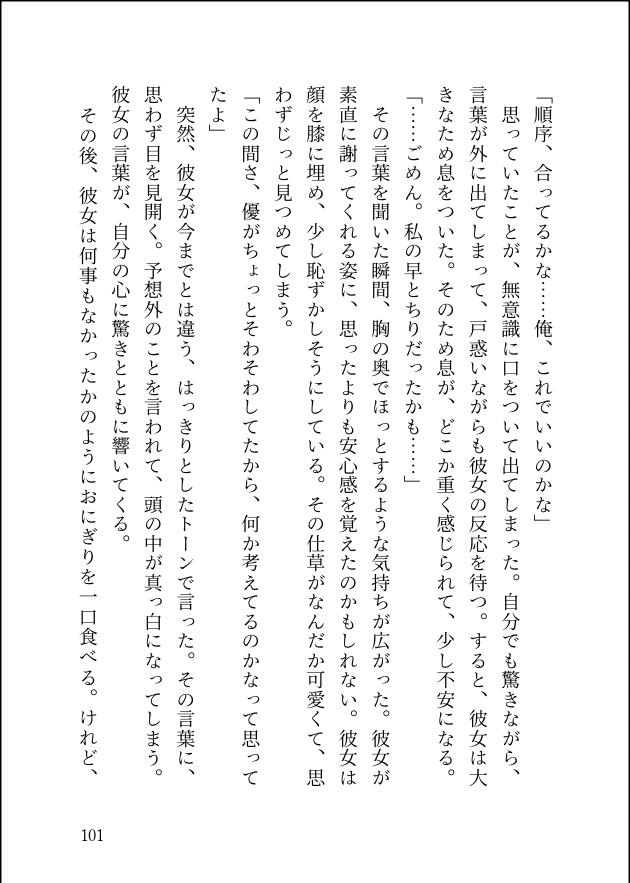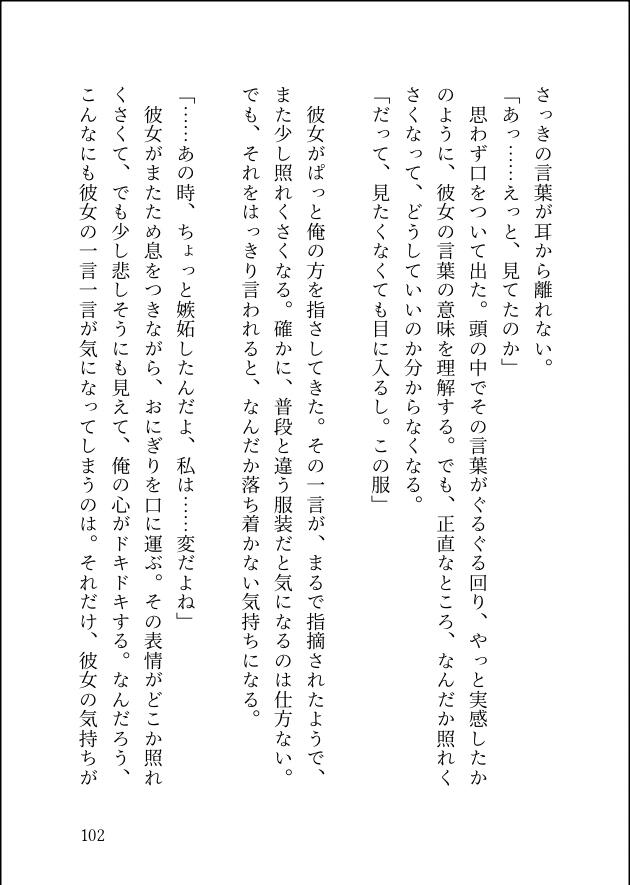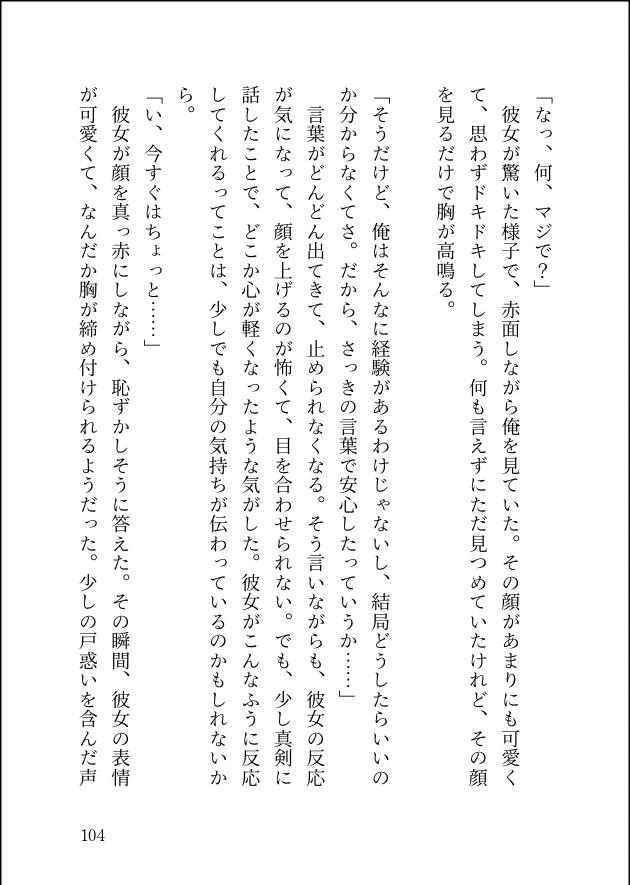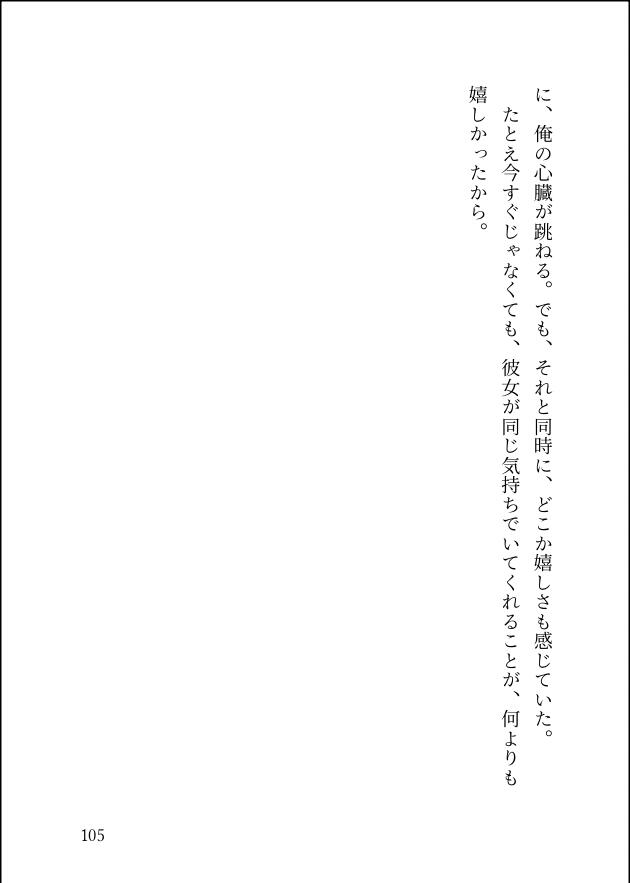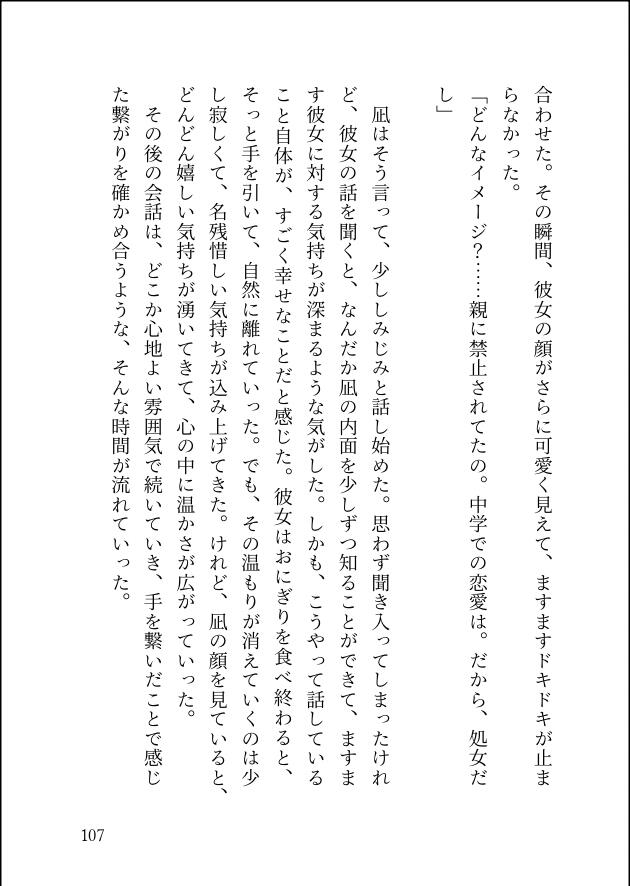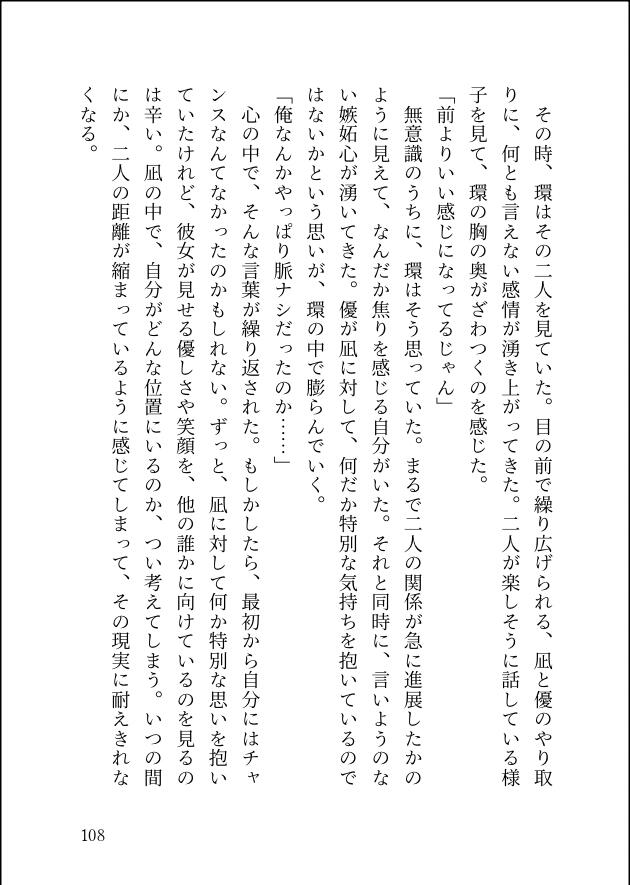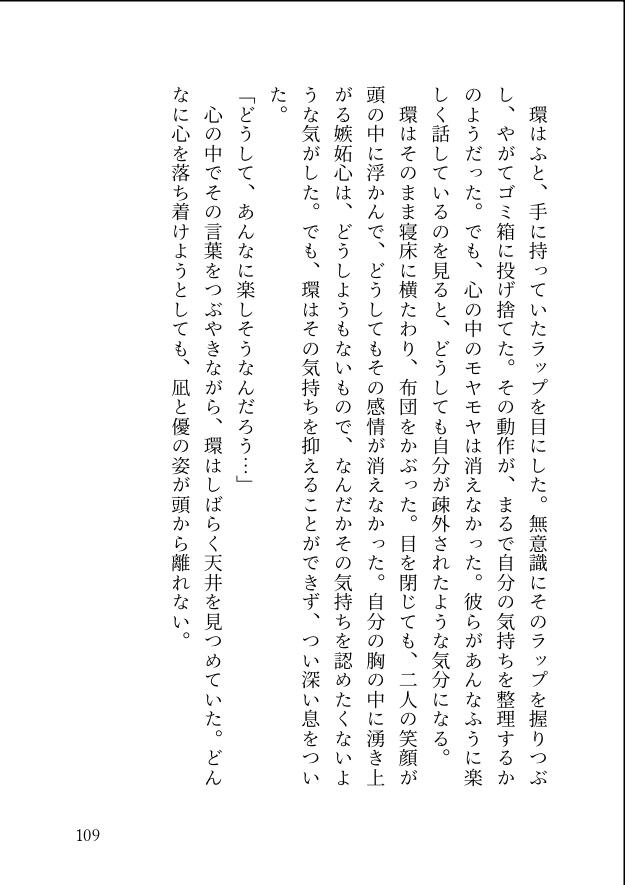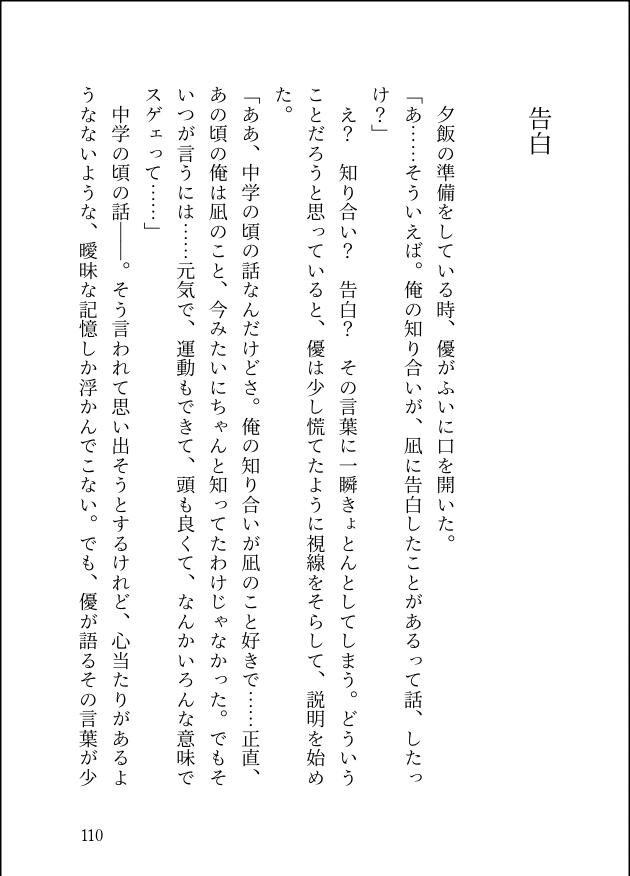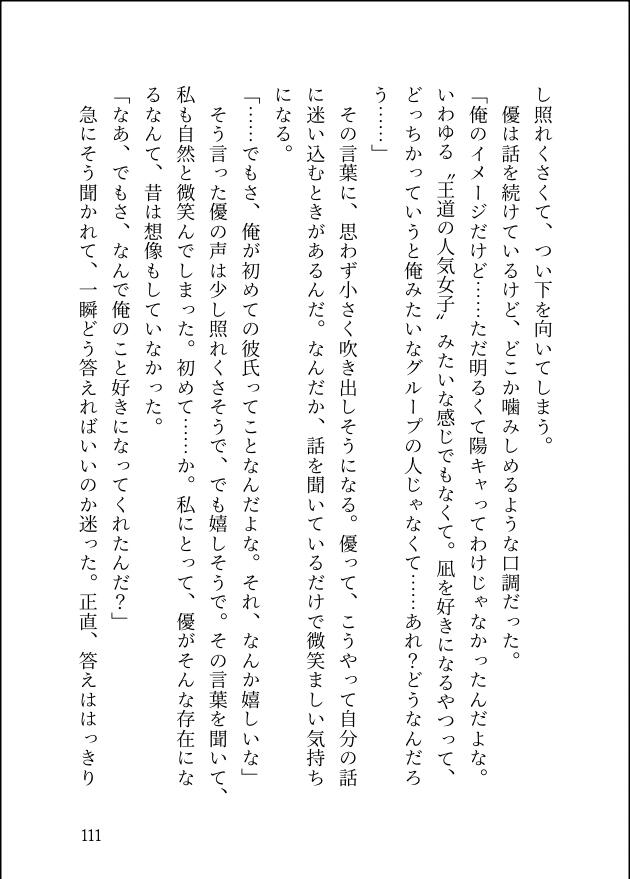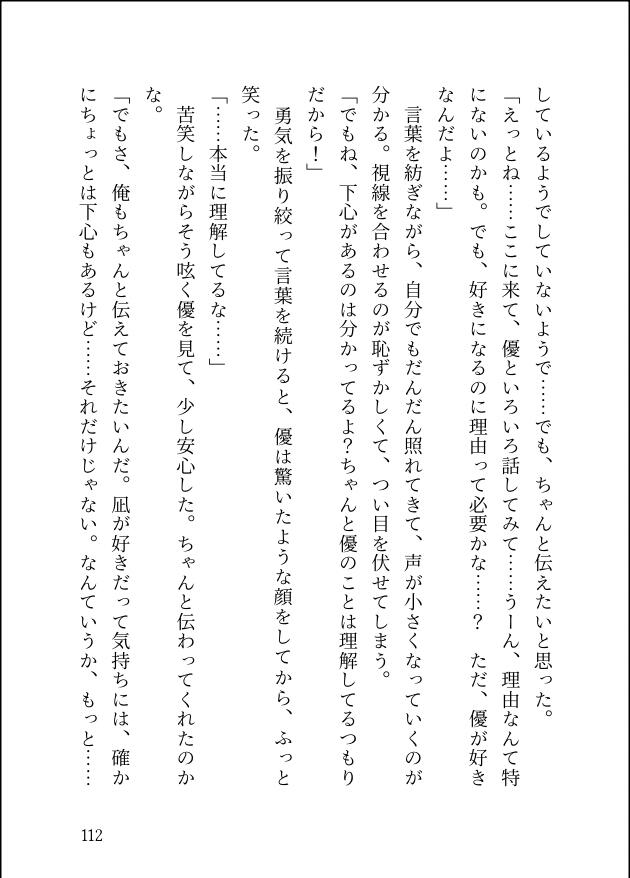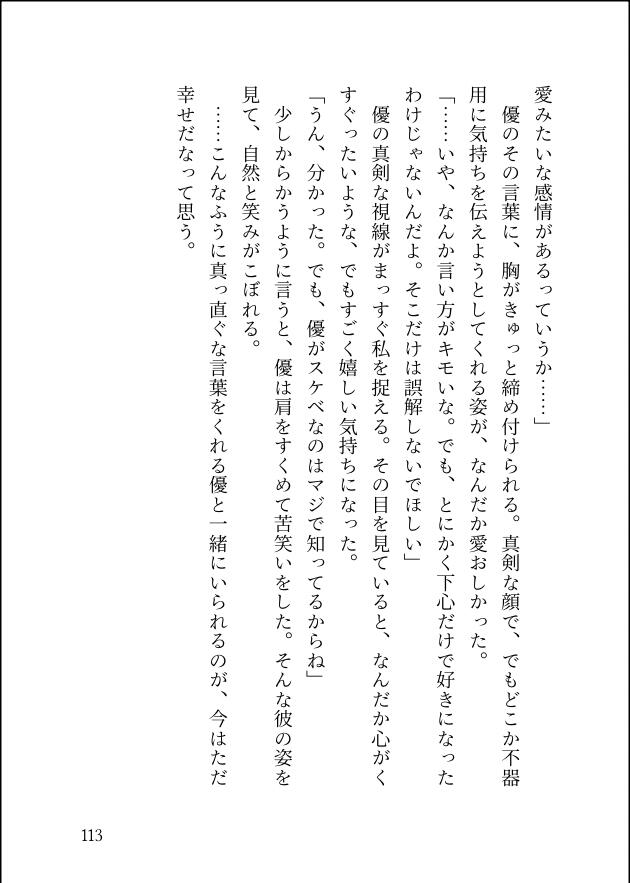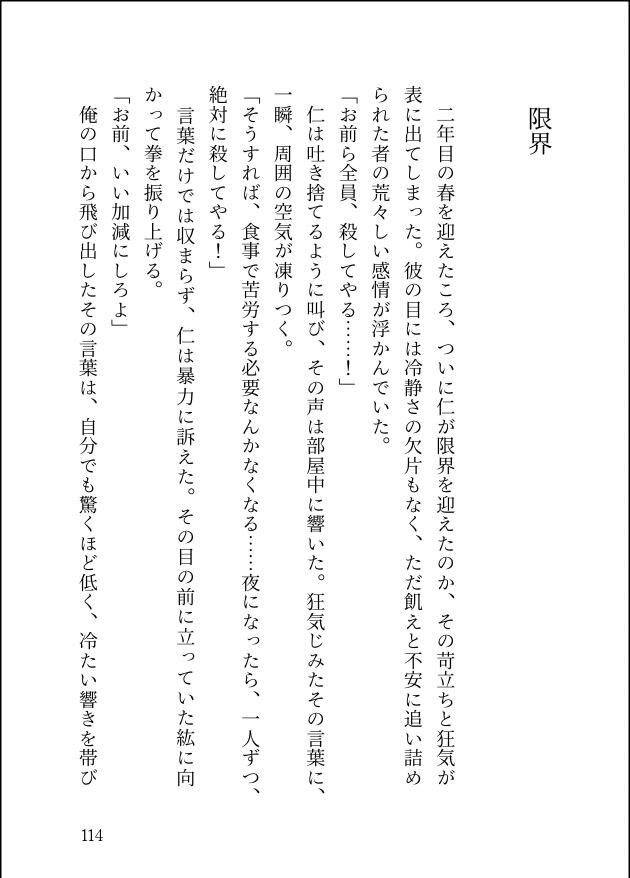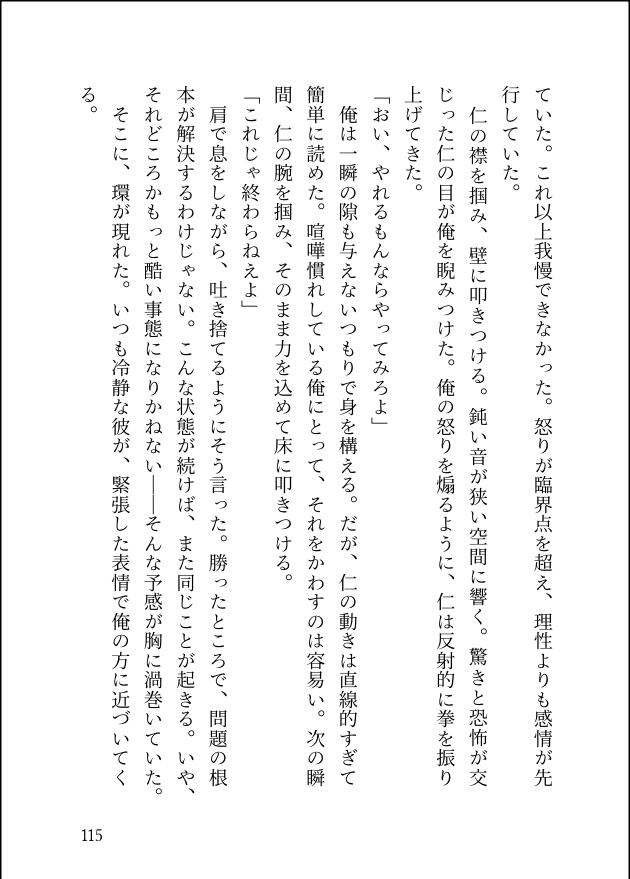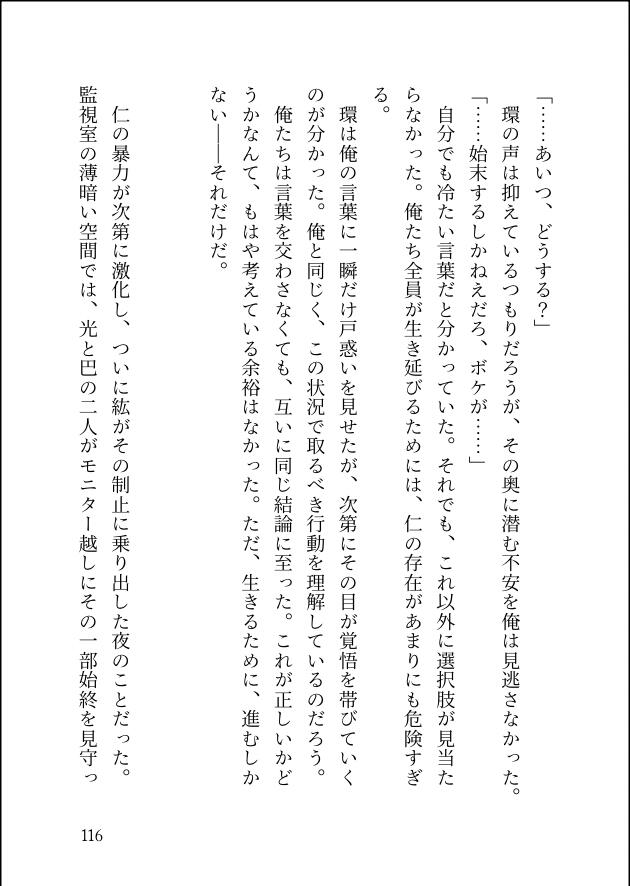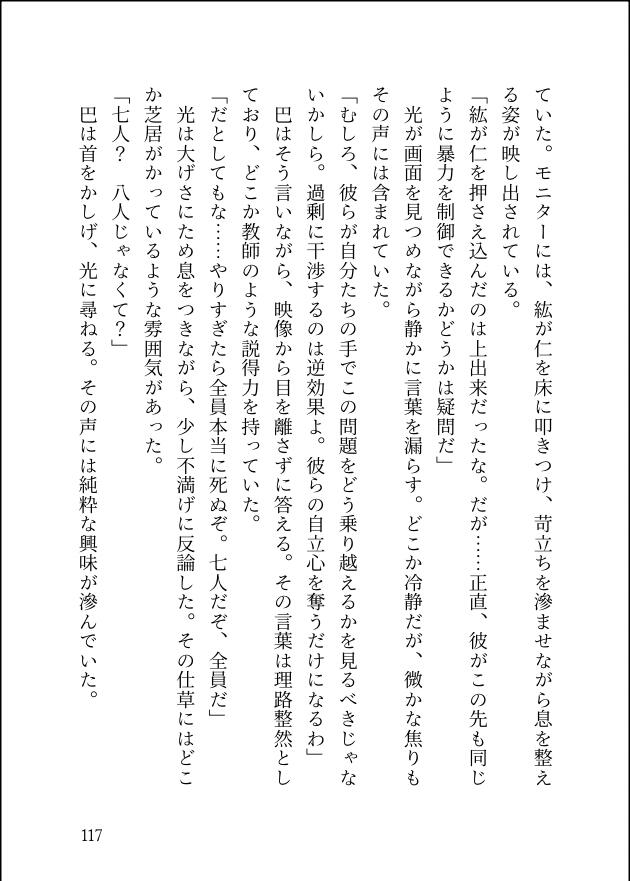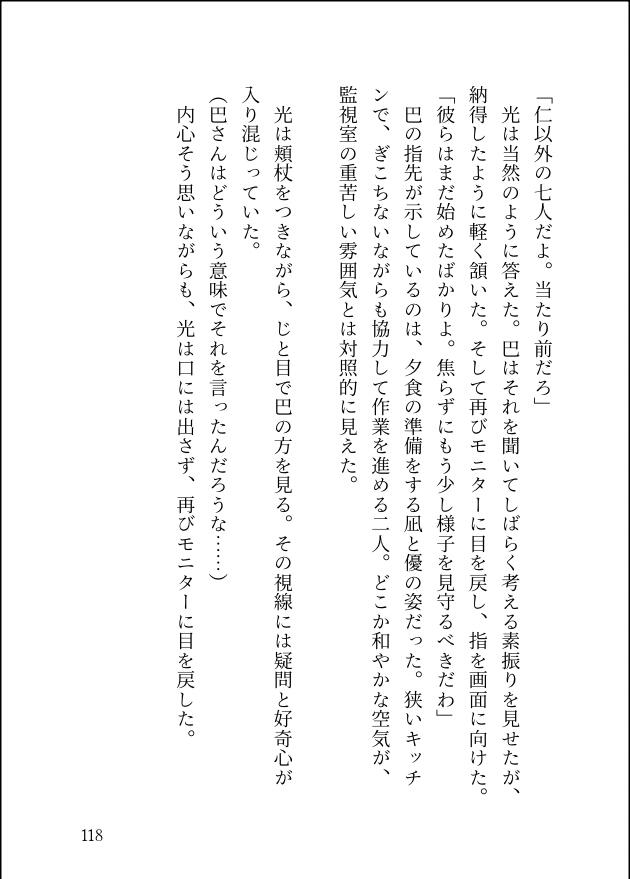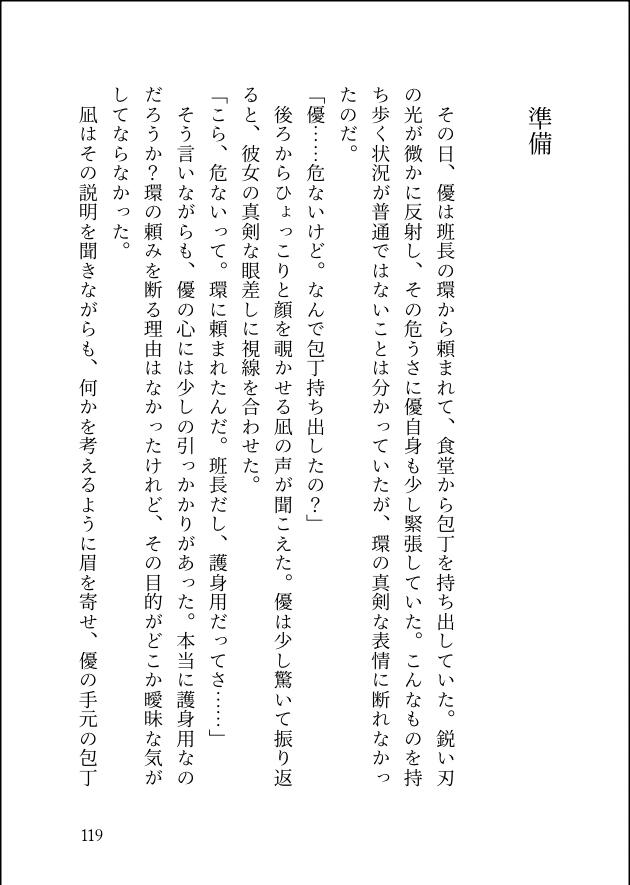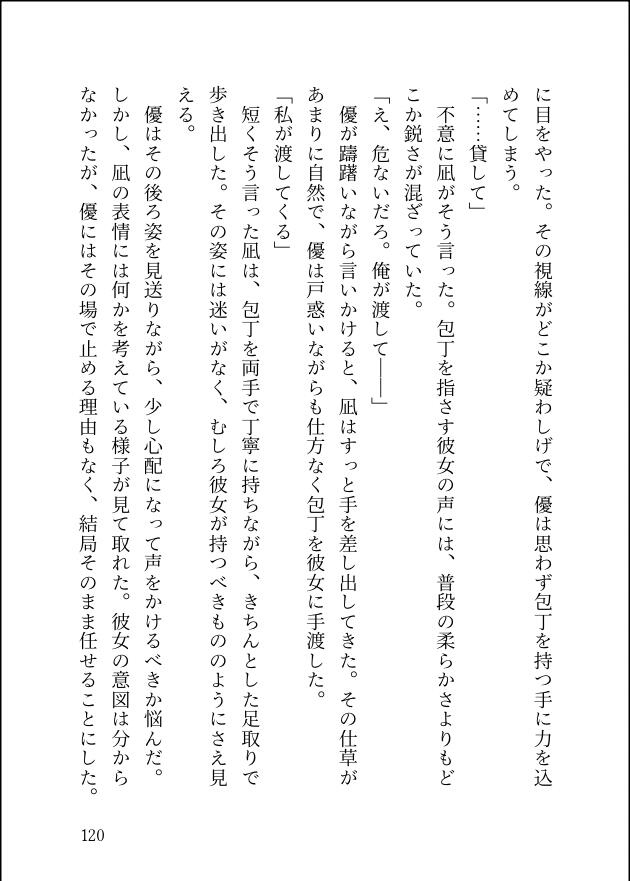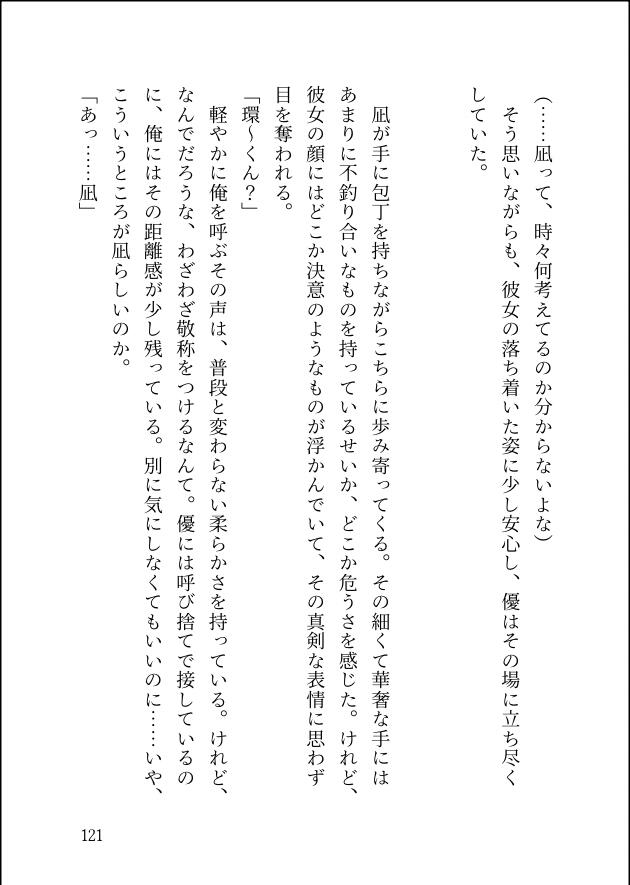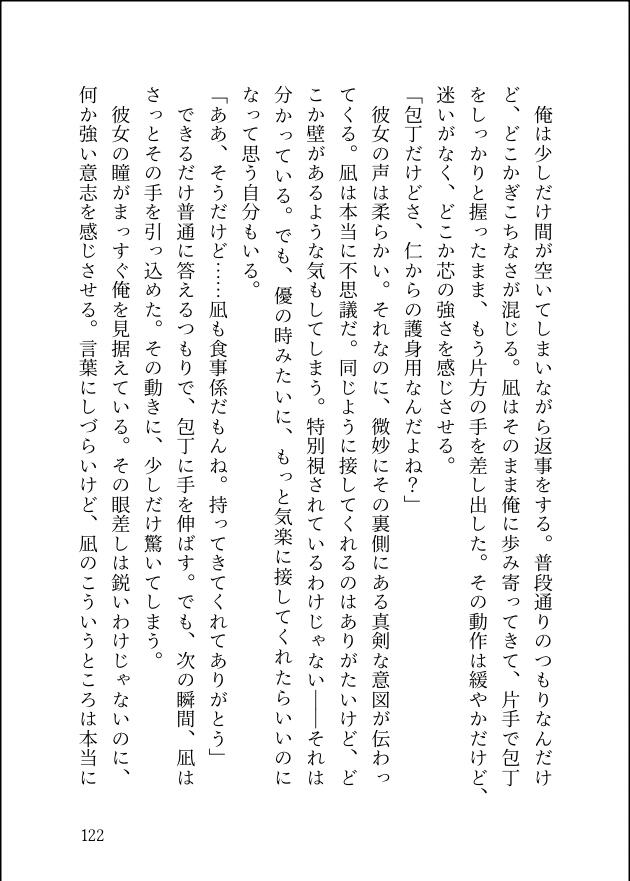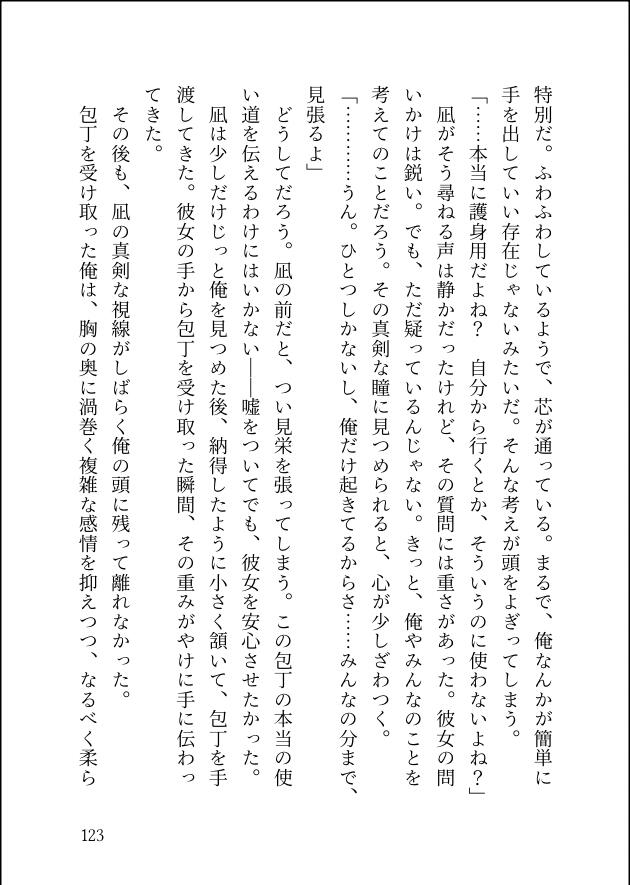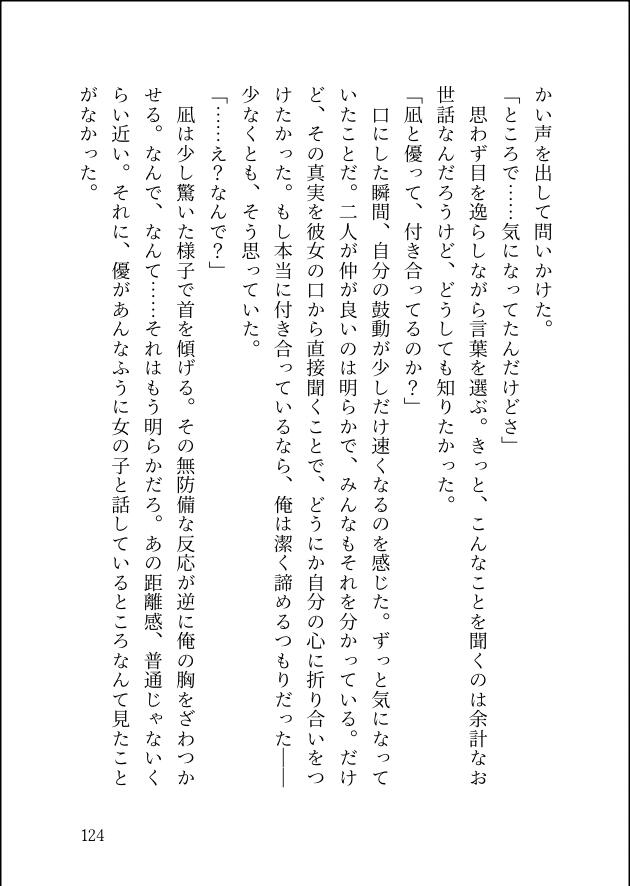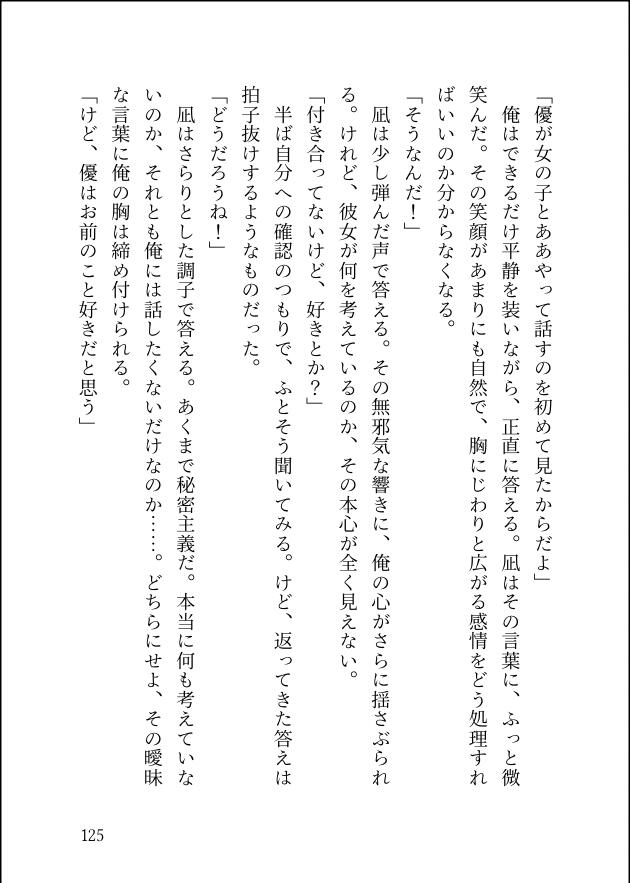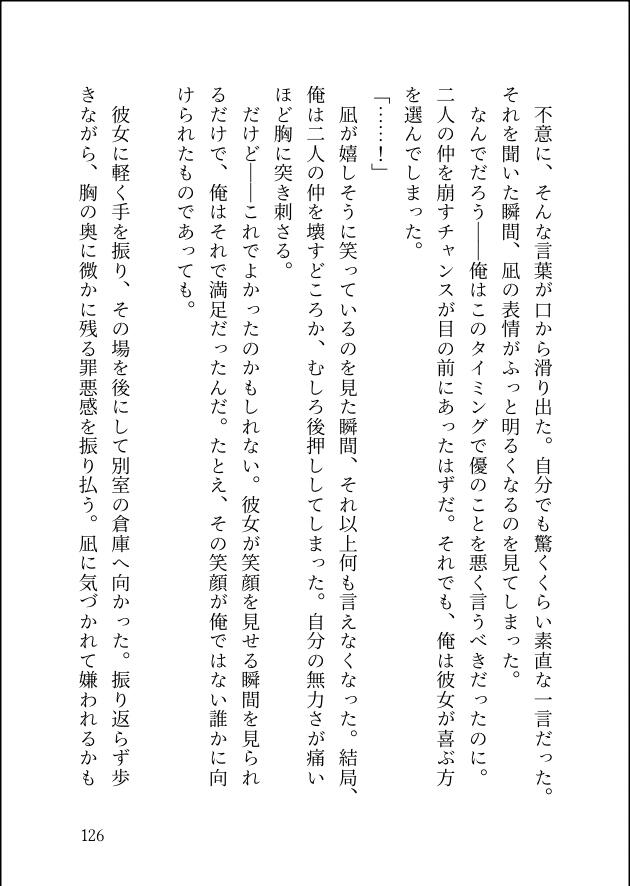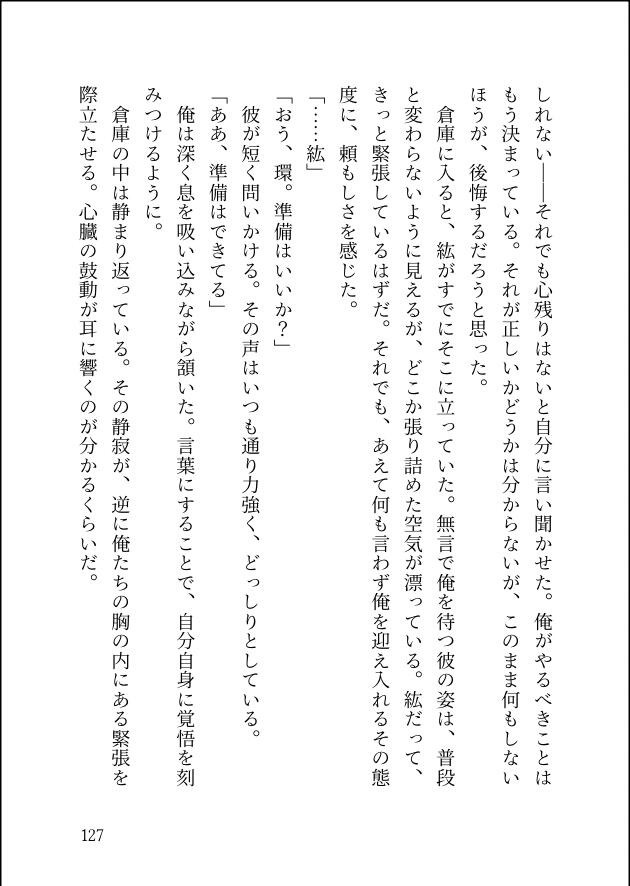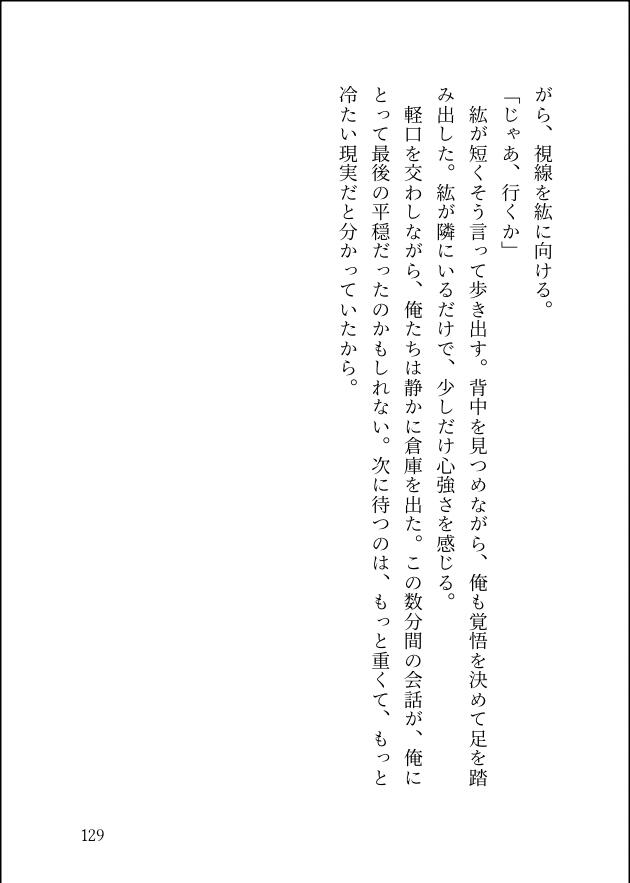第3章
〜省略〜
全年齢ver.に差し替えています。
ギリいけるので、元はコチラから
〜省略終わり〜
〜省略〜番外編として扱うのでコチラからどうぞ。
エクリプスの地下にあるエレベーター。ずっと行き先が限られていると思っていたその装置が、ある日突然、別の場所へと通じるようになった。行き着いた先は、図書館だった。
地下にこんな場所があったなんて、驚きもあったけれど、それ以上に私たちはこの空間をただの「暇つぶし」に使うことにした。たまには、閉塞感のある地下生活から少しでも解放されたい。そう思って、私は優と一緒に本を探していた。
広い図書館の中、私たちは黙々と本棚を物色する。けれど、どれもなんだか味気ない内容ばかりで、これといった掘り出し物が見つからない。
「優、そこの本……奥に手伸ばせる?」
少し高い棚の隙間に、なぜか無造作に落ちている一冊の本を見つけた。それを取るために、私は少ししゃがみ込んで、近くにいた優に声をかける。
「これか?」
優が私の声に応え、少し身を乗り出して腕を伸ばす。その時、ふと気づいた。
――なんでこんな時にメガネを外してるの?
探し物をしている途中でメガネがズレるのを嫌がったのか、彼はそのメガネをポケットに突っ込んでいる。それだけなのに、どうしてだろう。メガネをかけている時よりも、彼の顔がやけに整って見える。
ずるい。普段だってかっこいい顔してるのに、こういう時だけさらに際立つなんて。
「これだと思うけど……取れないな」
優が奥の本を取ろうと苦戦している。腕を棚の隙間に突っ込むたびに、彼の腕の筋がほんの少し動く。それだけで、私は妙にそわそわしてしまった。
――なんで、こんなに意識してるの?
彼の手の形、動き、そして真剣な表情。どれも特別なものじゃないはずなのに、目が離せない。その手で、私を……なんて、よくわからない想像までしてしまう。
――やめよう。こんなの……うん、やめよ。
一人で勝手に妄想を膨らませそうになる自分をなんとか抑え込む。けれど、私がそんなことを考えているとは知らない優は、まだ奥の本に手を伸ばしている。その腕が棚の角に当たって滑る――。
「っ!」
その瞬間、優の体がバランスを崩して倒れ込んできた。
「わっ!」
思わず私も仰向けになり、優の重みを全身で受け止める。柔らかな絨毯の上だから痛みはなかったけれど、問題はそんなことじゃなかった。
「ごめん、凪……大丈夫か?」
耳元で聞こえる優の声。その吐息が妙に熱を帯びているように感じる。
「う、うん……大丈夫だけど――」
慌てて答えようとしたけれど、そこで気づいてしまった。
――胸に……何か、触れてる。
いや、何かじゃない。優の手だ。完全に、胸を掴む形で触れている。触れるというより、もうしっかりとその感触を掴んでいるような状態。
「……っ!」
顔が一気に熱くなるのを感じながら、私は短く息を詰めた。
「ごめん!」
優もすぐに気づいたのか、慌てて手を引っ込める。でも、急に動いたせいで、かえってお互いの体勢がさらに乱れる結果に。
「ゔ」
彼の体がさらに私に押し付けられ、今度はお腹に何かが当たった。それは――。
「っ……!」
今度は、はっきりと感じてしまった。お腹越しに伝わるその存在感に、頭が真っ白になる。やばい。最悪の状況だ。
凪の胸に触れてしまったどころか、今度は俺の――いや、冷静になれ。言い訳しても仕方ないけど、本当にわざとじゃない。
「ご、ごめん!」
声が震えるのを感じながら、何とか体を起こそうとする。でも、密着したままの凪の柔らかな身体が余計に意識を狂わせる。
彼女の視線が、何かに気づいたように鋭くなるのを感じた。
「……これ、何が当たってるの?」
小さな声で囁かれるその一言に、俺は完全に動きを止めた。
「いや、それは――」
言い訳しようにも、言葉が出てこない。
「優……ちょっと正直に言ってみてよ」
凪の声は震えている。でもその震えが怒りではなく、微妙に揺れる感情から来ていることを、俺は感じ取った。……わかってるくせに。
その瞬間、視線が交わる。近すぎる距離で、俺たちはお互いの息遣いまで感じていた。優の目が、いつもと違って鋭い色を帯びていた。今この瞬間、彼の中で何かが揺れているのがわかる。
でも、揺れているのは私も同じだ。彼の手の感触がまだ胸に残っている。それだけじゃない――さっきお腹に感じた存在感が、嫌じゃなかった自分に気づいてしまったのだ。
「……メガネない方が、カッコいいじゃん」
反射的に出た言葉が、私たちの間の空気をさらに濃密にした。
「そんなこと言ってる場合か……」
優が顔を赤くしながら呟く。でも、その声には少し余裕がなかった。
「優……わざとじゃないのはわかってるけどさ……」
私はそっと胸元を押さえながら、彼に近寄る。
「責任、取ってくれるんだよね?」
彼が呆然とした顔をするのを見て、私は口元を抑えて笑った。意識してるのは私だけじゃない。その事実に気づいた時、妙に嬉しくなったのだ。
優は、私を本棚に思いっきり詰め寄った。その瞬間、私の胸が一気に高鳴るのを感じた。彼がぼそりと口にした言葉が、何だか胸に響く。
「責任取る……けど」
顔が赤くなっているのが、なんだか可愛らしくて、思わず息を呑んだ。彼の目は真剣だけど、恥ずかしそうに俯いていて、なんだか心がドキドキしてきた。
そのまま、優は何の前触れもなく、本棚に私をぐっと押しつけるように手をついて、所謂“壁ドン”の体勢を作った。私の視界が急に暗くなって、気づけば優は少し私を見下ろしている位置に立っていた。その身長差に、改めて驚く。こんなに差があったっけ? 彼の顔がぐっと近づいてくるのを感じ、私は自然と息を止めた。
その瞬間、優が私の顎に手を添えて、ゆっくりと顔を引き寄せ、唇が重なる。最初のキスは、思ったよりも優しく、温かいもので。何も考えられなくなって、ただその感覚に身を任せていた。唇が離れた後、私はぼーっとして、しばらくその場に立ち尽くしてしまった。まるで世界がふわふわとした感覚に包まれて、頭が回らない。
何とか目線を下に落とし、足元を見たけれど、焦点が合わない。そんな顔を優に見られるわけにはいかない、と思うと、ますます顔が熱くなる。まるで、照れてしまう自分が恥ずかしくて仕方なかった。
「……今日はこれだけ」
優はそう言って、私の頭をそっと撫でてくれた。その仕草が嬉しくて、自然に顔を上げる。目を合わせた瞬間、私の心臓が急に高鳴る。そのとき、気づいたら私は優の胴体に抱きついていた。自分でも驚くほど、自然に体が動いてしまった。でも、それが何だかすごく安心する。
私、抱き癖があるって分かってたけど、こんな無自覚に抱きついてしまうなんて。思わず頭を優の胸にぐりぐりと押し付けてしまう。もう、こんなに近くにいることが、心地よくてたまらなかった。
優は少し驚いたように、でもそのまま腕を私の背中に回してくれた。彼の温もりが私に伝わってきて、しばらく沈黙の時間が続く。けれどその静かな空間は、私にとって本当に落ち着くひとときだった。何も言わなくても、お互いに通じるものがあるような気がした。
ふと、彼の鼓動が速くなっていくのを感じた。何だか私の心臓までその音に合わせて速くなる。少し驚いて、手を優の胸に当てると、彼の心臓の音がよく聞こえる。
「すごくドキドキしてる? いつもこう?」
なんとなく聞いてみた。優は少し照れたように顔を赤らめ、少し困ったように答えた。
「いつもなわけないだろ」
その答えに、思わず微笑んでしまう。優が少し恥ずかしそうに笑っているのを見て、私はまた胸がいっぱいになった。けれど、その後、優が顔をしかめて言った。
「人が来たらまずい」
私たちは仕方なく離れることになった。少し寂しかったけれど、今日はこれだけでも十分すぎるほど幸せだった。優と過ごしたこの時間が、私にはとても大切で、心に残るものだった。
二人で本を取り、再び部屋へ戻る。すれ違う時、優の背中を感じながら、私は少し笑顔をこぼした。こんな日が、ずっと続けばいいのに。
「順序、合ってるかな……俺、いいのかな」
思っていたことが、無意識に口をついて出てしまった。自分でも驚いているうちに、言葉が外に出てしまって。そんな自分に少し戸惑いながらも、彼女の反応を待った。すると、彼女は大きなため息をついた。そのため息が、どこか重くて、ちょっと不安に感じる。
「……ごめん。私の早とちりだったかも……」
その言葉を聞いた瞬間、なんだか胸の奥でほっとするような気持ちが広がった。彼女が素直に謝ってくれるその姿が、思ったよりも安心感をくれたからだろうか。彼女が顔を膝に埋めて、少し恥ずかしそうにしているのが見えた。それがなんだか、すごく可愛く見えて、ついその姿をじっと見つめてしまう自分がいた。
「この間さ、勃ってたから、好きな子となんかしたくて堪らないのかと思ってたよ」
突然、彼女が今までとは違う、はっきりとしたトーンで言ってきたその言葉に、俺は思わず目を見開いた。予想外の言葉だったから、頭の中がしばらく真っ白になってしまう。その言葉が耳に届いた瞬間、心臓がドキッと跳ねるのが分かる。彼女の言葉が、驚きと一緒に、どこか自分の胸に響いてきた。
その後、彼女はすぐにおにぎりを一口食べて、何事もなかったように続ける。けれど、その言葉が耳から離れない。
「あっ……えっとな、見てたのか」
俺は思わず口から出てしまった。頭の中でその言葉がぐるぐる回っていて、やっと実感したかのように、彼女が何を言っているのかが理解できた。でも、正直なところ、なんだか照れくさい気持ちが込み上げてきて、どうしていいか分からなくなる。やっぱり、マジでスケベなんじゃないかと思ってしまう自分もいる。でも、考えてみれば仕方ない。あんな格好をしていたし、見たくなくても目に入ってしまうだろう。
「だって、見たくなくても目に入るし。この服」
彼女がぱっと俺の方を指さしてきた。その一言が、まるで指摘されたようで、また少し照れくさくなる。確かに、あんな服を着ていれば、目が行くのも無理はない。けれど、どうしても目が行ってしまう自分もいる。お互い様だ。何度も目を反らしては、無意識に視線を戻してしまう。どうしても気になってしまう。
「あの時嫉妬したんだよ、私は……愚かだなぁ」
彼女がまたため息をつきながら、おにぎりを口に運ぶ。その表情が、どこか照れくさくて、少し悲しそうにも見えて、俺の心がドキドキしてしまう。なんだろう、こんなにも彼女の一言一言が気になってしまうのは。それだけ彼女の気持ちに引き寄せられているからだろうか。
「俺……ちょっとキモいこと言っていい?」
その言葉が口をついて出た瞬間、なんだか自分でも驚いた。ああ、もう言ってしまった、と思ったけど、でも、気持ちが溢れてきて、どうしても言わずにはいられなかった。でも、心の中ではまだ少しだけ緊張している自分がいる。それに、彼女にどう思われるかが気になって、少し怯えていた。
「いいけど……私が1番キモいこと言ったし」
彼女がそう言ったのを聞いて、どこか安心した気持ちが広がった。なんだか、彼女も緊張しているんだろうな、って感じたからだろうか。だから、少しだけ心の中で気持ちが楽になった。彼女の言葉をきっかけに、少し気が抜けたような気がした。でも、やっぱりまだどこか恥ずかしさが残っていて、なんだか上手く言葉が出ない。だから、俺はそのまま、もう一度言葉を続けることにした。
「両想いになったらすぐ抱きたいってずっと思ってた」
その一言を口にした瞬間、彼女がむせていた。思わず目を見開いてしまったけど、なんだか胸が締め付けられるような気がして、急に照れくさくなった。自分の言葉がどれだけ突飛だったのか、少し後悔したけれど、彼女がどう反応するのかが気になって仕方がなかった。
「なっ、何、マジで?」
彼女が驚いた様子で、赤面しながら俺を見ていた。その顔があまりにも可愛くて、思わずドキドキしてしまう。何も言わずにただ見つめていたけど、その顔を見ているだけで胸が高鳴って、どうしても顔が赤くなるのを感じた。
「そうだけど、俺童貞だし、結局いつ手を出せば良いかわかんないと思うから、さっきああ言われて安心したっていうか……今すぐにでもっていうか」
言葉がどんどん出てきて、なんだか止められなくなった。そう言いながらも、彼女の反応が気になって、顔を上げるのも怖くて、目を合わせられない。でも、少しだけ真剣に話したことで、どこか心が軽くなったような気がした。だって、彼女があんな風に反応してくれるってことは、少しでも自分の気持ちが届いたってことだろうから。
思わずそのまま、止まらなくなって言ってしまった。今すぐにでも彼女と何かをしたい。でも、やっぱりそれには時間が必要だし、どうしたらいいのか分からなかった。
「い、今すぐはちょっと……」
彼女が顔を真っ赤にしながら、恥ずかしそうに答えていた。その瞬間、彼女の顔に浮かんだ照れくさい表情が、何だか可愛くて胸が締め付けられるようだった。少しの戸惑いを含んだその声には、心の中で何かが湧き上がるのを感じたけれど、それでもその言葉には嬉しさが強く感じられた。たとえ今すぐでなくても、彼女がその気持ちを少しでも持ってくれていることが、心の中で何度も響いた。